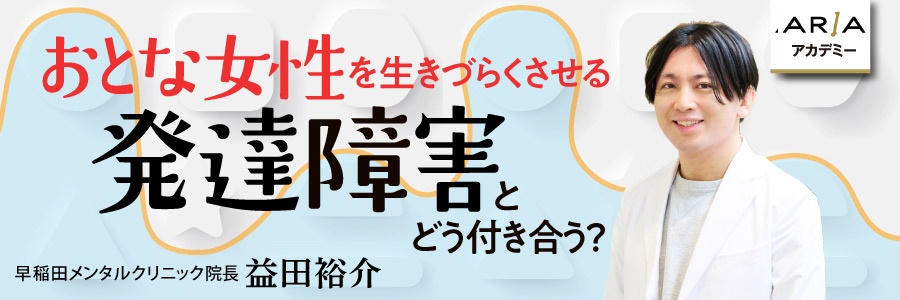「見えないへその緒」が、プツッと切れた
小川 母が亡くなったことで、見えないへその緒がようやく切れたような、解放された感じがしました。同時に、母の存在が私の中に入ってきて、今はむしろずっと近くにいるような、そんな感覚があります。おかしな表現かもしれませんが、胎内に母を宿しているような感じです。
そんな温かな感覚を受け取れたのも、母の死が与えてくれたギフトだったと思います。母の死を経て書き始めたこの『ライオンのおやつ』でも、死がもたらすものが苦しみやつらさばかりではないことを描きたいと思いました。
最初にお話ししたように、今は、母もそうでしたが病院で亡くなる人が多いので、死そのものが普段の生活から切り離されています。生と死はつながっていて、本来身近にあるもののはずですが、隠されて得体が知れないものになってしまっているために、余計に怖さが増しているように思います。その得体の知れなさとそこから来る怖さが少しでも和らぐような物語にしたかったのです。
どれだけ体が弱って残された時間が短いとしても、生きていれば喜怒哀楽があり、幸せを感じる瞬間も、変わるチャンスさえあるということも描きたいと思いました。また、たとえばパズルのピースがひとつ失われても周りのピースによって元の形が浮かび上がるように、亡くなった後、体は失われても周囲の人に残されるものがあるということも、描きたかったことです。
今回、設定を「最後の食事」ではなく「最後にもう一度食べたいおやつ」にしたのは、おやつは体にとって必要不可欠なものではない分、豊かな思い出に結びついていることが多いと思うからです。自分にとってのそんな「おやつ」を考えようとすると、忘れていたことが思い出されて、自分の人生にも幸せな瞬間があったことに気づけるのではないかと思ったのです。
―― 小川さんにとってそんな「おやつ」はありますか。
小川 祖母が作ってくれたものが候補なのですが、なかったと思っていた母との間にもそんなおやつの記憶があったことが思い出されて、実はまだ決めかねています。いろんなことを思い出しながら、ゆっくり考えてみようと思っています。
続きの記事はこちら
⇒小川糸 「自由に生きていい」が心地いいベルリンの生活
取材・文/宮本恵理子 写真/洞澤佐智子