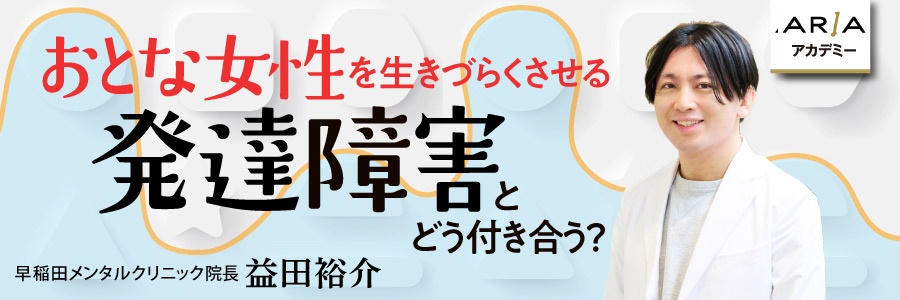命に限りがあることをありがたく感じて
小川 母が病気になり、死にゆくことが分かってから、私と母の関係がクルッとオセロを返すように変わっていったんです。
物心ついたときから、母は私にとって強大で威圧的な存在でしたが、亡くなる数カ月前には認知症の症状も出始め、私のことも分かっているのか分かっていないのか、という状態になりました。その時、母のことを初めていとおしく思えたのです。
もしも人間に寿命がなく、母が永遠に生きていたとしたらあの転換はもたらされなかったのだと思うと、命に限りがあることをありがたく感じました。
―― 亡くなる前のやりとりで特に印象に残った会話はありますか。
小川 だいぶ弱ってきた頃に、お見舞いに行って一緒に過ごしていると、突然「もう遅いから新幹線で帰りなさい」と言い出して、自分の荷物の中から小銭を取り出して、私に渡したんです。
たった数百円で帰れるわけがないけれど、そのときの母にとって精いっぱい、私にできることをしてくれたんだなと思えました。小学生の頃、「クリスマスプレゼントよ」とのし袋に1万円を入れて渡す母のことを、私は遠ざけてきたけれど、もしかしてそれが母にとっては不器用な愛情表現だったのかもしれないな……と。
そんなことを思いながら、病院を出て駅に向かう途中、懐かしい喫茶店が視界に入ってきました。そこは、子どもの頃、母の日や母の誕生日に、私が母を連れてきてケーキをごちそうしていたお店でした。
母からもらったお金を使って、私も私なりに母を喜ばせようとしていた。そうか、子どもの頃の私は、母のことが好きだったんだなって初めて気づいて。小銭を握り締めてお店の中に入って、号泣しました。