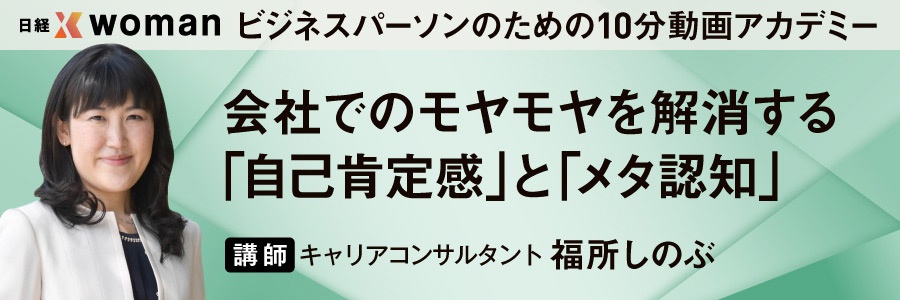誰かにとっての救いになる映画を作りたかった
早川 「なんで白黒の昔の映画を子どもに見せるんだろう」とか、「もっと面白そうなストーリーがいい」と最初のうちは文句を言っていたんですが、見ているうちにどんどん引き込まれていって。登場人物のささいな感情まで丁寧に描かれていて、子どもながらに「その感じ、分かる!」と共感を覚えました。
この映画を作った人は、私の気持ちを分かってくれている。そんな気がして、救われた気持ちにもなれました。映画の中の世界は、時代も登場人物がいる場所も違うのに、なぜ心が通じ合えるんだろうと不思議に思って。もっとこういう体験がしたいと思い、それからいろんな作品を見るようになりました。
―― その出来事は監督にとっての「原体験」なんでしょうね。
早川 まさに、原体験です。映画の存在に私自身、救われたところがあるので、誰かにとっての救いになる映画を作りたいと思うようになりました。中学生の頃ですね、そう思うようになったのは。
例えば、『PLAN 75』だったら、主人公の角谷ミチ(倍賞千恵子)さんと似たような境遇の人が観客の中にいて、「あ、ここに私がいる」「私の気持ちをすくい取ってくれている」と思ってもらえたらうれしいなって。そういう思いでこれまで映画作りをしてきたように思います。
―― 映画を作りたいと思うようになってから、どのようにして映画の道に?