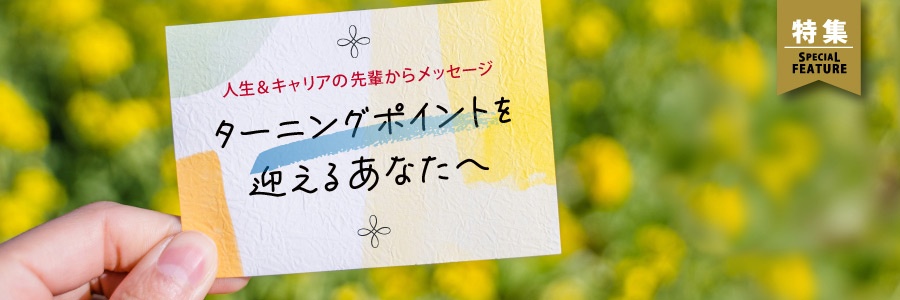30代でアナウンサーを辞め、弁護士という新しいフィールドに挑戦した菊間千乃さん。自らの手でキャリアを選択してきた菊間さんが、心に響いた言葉や感じた事柄について語ります。今回のテーマは「聞く力」です。
「菊間さんだと、ついしゃべっちゃうんだよね」と言われることがあります。アナウンサー時代も「テレビのままですね」と驚かれ、ほかでは話してないことや、深い話を聞けることがありました。私に「聞く力」があるとしたら、私自身は何も隠そうとしないし、人に対して壁をつくらないようにしているからだと思います。
寡黙な父を冗舌にするインタビュアーへの憧れ
そもそもアナウンサーになりたいと思ったきっかけは父でした。高校バレーの監督をしていた父はよく記者やアナウンサーから取材を受けていました。家では寡黙な父を冗舌に語らせる記者ってすごい、というのが私の感動ポイントでした。
でも、父をよく見ていると、熱心に話したり、そっけなくしたり、相手によって態度を変えていたのです。小学校3年生の私が「お父さん、みんなに平等に話さないのは良くないよ!」と注意したら、父はこんなことを言いました。
「努力して勉強してきている記者は、きっとバレーボールを世の中に広めるいい記事を書いてくれるだろうから、熱心に話す。でも、たいして調べもせず、ただ担当になったからといって来るような記者には、大事な時間を割きたくない」。なるほど、相手の心を開くのは自分の努力や心掛け次第なのか。その言葉を聞き、子どもながらインタビューの仕事って面白いと思ったのです。
アナウンサーになってからは、既定路線ではなく、他では出ていない話を少しでも引き出したいと考えていました。相手のことを調べて、聞きたいことを書き出した上で、インタビュー時には手元は見ないように頭に叩き込んで臨みます。
インタビューは生ものです。相手の方が今、この瞬間に話したいと思っていることがあるかもしれないのですから、もともとのインタビューの目的プラスαの部分が大切だと思っていました。予定調和のインタビューってつまらないじゃないですか。
生放送のスタジオも同じ。生放送なのに収録番組のようにガッチガチに台本があるのはおかしいのではないかなと。放送の目的がきちんと伝われば枝葉末節は気にしない。そんなわけで、スタッフからは台本通りにやらない「壊し屋」と嘆かれていました(笑)。相手と自分の魂が触れ合って話を引き出したい。インタビューってそういうものだと思います。
そんな私ですが、「これではインタビューができない」と真剣に悩んだ時期がありました。