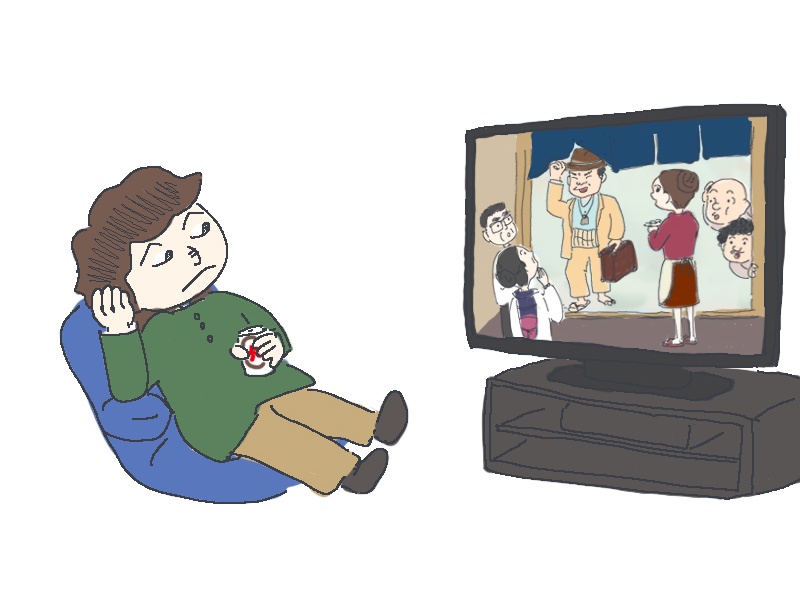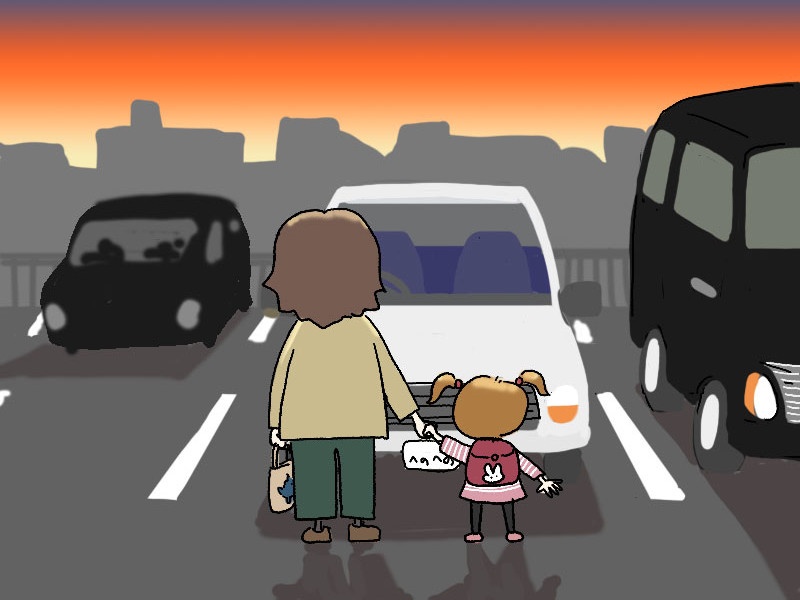「死んだ後、寂しくないべか」
思い出すのは、母方の祖母のことだ。87歳まで生きた。晩年は認知症を患い、家族の顔を含めてさまざまなことを忘れてしまったが、病の前も後も穏やかな性格は変わらなかった。常に自分より周りの人を優先し、むやみに声を荒らげたり怒ったりする姿を見たことがない。
その祖母が、亡くなる少し前にしきりに口にしていたことがあった。
「死んだ後、寂しくないべか」
残された家族が、ではない。一人で死ぬ自分が寂しくないかを心配しているのだ。そう気づいた時、果てしないような気持ちになった。すべてを見通して終わる人などどこにもいない。いるのは、ただ未知の扉の前に立つ一人の人間だと知ったからだ。
今もまだ面倒事は続いている。人生にはあといくつ扉が待ち受けているのか。そしてその向こうにはどんな景色が広がっているのか。明るい空か、暗い淵か、輝く月か。見たことのない景色は、恐ろしいけれど少し楽しみのような、いややっぱり楽しみじゃないような、複雑な日々である。
ちなみに私の五十肩は、先人の言うとおり「いつのまにか」治っていた。去年の9月、大風で吹っ飛んだ部屋の換気口の蓋を修理しようとした時に足を滑らせて脚立から落ち、肩に尋常ならざる痛みが走ったのだが、その日を境に徐々に痛みが薄らいだのだ。何か新しい治療法を発見してしまったかもしれないとも思ったが、そんなはずはなく、大風のすぐ後に地震があり、さらに父が死んだりして、仕事を休んでいたのがいい方に作用したのだろう。有給休暇ではなかったことだけが残念である。
文/北大路公子 イラスト/にご蔵