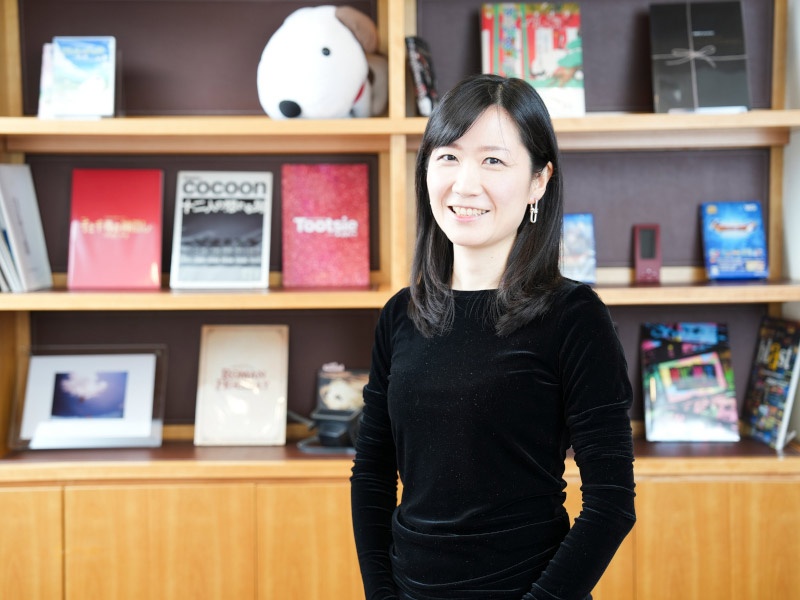ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の演奏が終わると、下関市民会館の満席の会場がシーンと静まりかえって、そこにいる全員の心が一つになったように感じました。「これほどまでに人の心を動かす音楽って一体何だろう?」。それを知りたくなって、音楽学部に進むことを決めました。
進学したのは、長崎の活水女子大というキリスト教系の歴史ある学校。西洋音楽はキリスト教文化の中で育まれたものなので、カトリック教会の数が全国で最も多く、異国情緒あふれる長崎の街は学ぶのにうってつけの環境でした。
「音楽とは何かを知りたい」早朝から勉強漬けの日々
大学時代は図書館にある音楽に関する本を1冊残らず読みました。音楽に限らず、作曲家が影響を受けた文学作品や歴史の本、外国語で書かれた音楽の本にもくまなく目を通しました。毎朝寮を出て6時38分発のバスに乗り、7時に開門するのと同時に学校へ入って勉強するという生活を卒業まで続けました。
ピアノも1日最低6時間は練習していました。例えばビジネス書をいくら読んでも、MBAを取りましたと言っても、現場を知らないコンサルタントが経営改革なんてできないですよね。それと一緒で、知識だけ深めても音楽を知ることはできません。ドビュッシーの音楽を知るためには、五線譜に書かれた音符と向き合い、奏でて、聴いていただく。音符を立体化して「相手に届ける」という行為があるのとないのとでは全く違います。
なおかつ、ドビュッシーを演奏するに当たっては、同時代のマラルメ、ヴェルレーヌといった19世紀に活躍した詩人の存在は欠かせません。「ドビュッシーはこのヴェルレーヌの詩にある鐘の音を表現したんじゃないだろうか」といったように、一人の音楽家を通じて、詩の世界も知ることができました。
とはいえ二十歳そこそこで、音楽とはなんぞやということがそうそう分かるはずもありません。それでも毎日必死で楽譜や本に向かう中、あるとき図書館で出合ったのが、作曲家・三善晃さん(1933~2013)の『遠方より無へ』というエッセーでした。