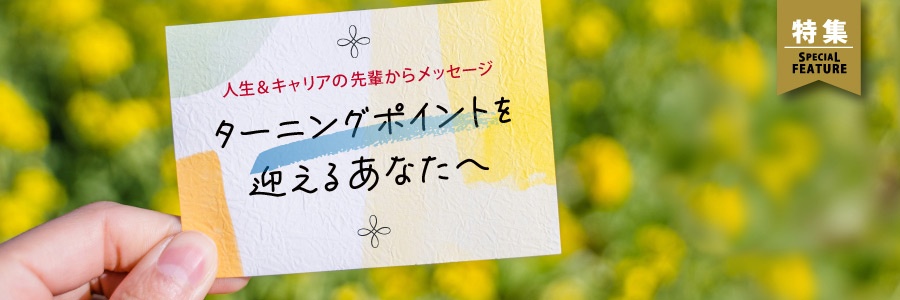人生には思いもよらぬことが起きるもの。肩の力を抜いて柔軟に「私の生き方」を見つけていこう――。先輩たちが半生を振り返って贈る、珠玉のメッセージ。日経WOMANの看板リレー連載を、日経ARIA読者にお届けします。エッセイストの平松洋子さんは10代のころ本を次々と読むことで、集団行動で感じる息苦しさから逃れていました。進学して上京、社会学を学ぶうちに「調べて書くこと」の面白さに目覚め、在学中からライターとして仕事を始めます。
(1)本が息苦しさから私を自由にした ←今回はココ
(2)仕事であがいた先に「次」がある
(3)「自己表現」にはこだわらない
エッセイスト
 1958年岡山県生まれ。東京女子大学在学中からライターとして仕事を始め、卒業後、食文化や暮らしをテーマに、アジアを中心に世界各地を取材。『とっておきのベトナム家庭料理』(マガジンハウス)など現地の食卓を紹介した本が注目を集める。2006年に『買えない味』(筑摩書房)でBunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。2012年に『野蛮な読書』(集英社)で第28回講談社エッセイ賞受賞。『サンドウィッチは銀座で』(文藝春秋)などエッセイが常に人気。最新刊『忘れない味 「食べる」をめぐる27篇』(講談社)
1958年岡山県生まれ。東京女子大学在学中からライターとして仕事を始め、卒業後、食文化や暮らしをテーマに、アジアを中心に世界各地を取材。『とっておきのベトナム家庭料理』(マガジンハウス)など現地の食卓を紹介した本が注目を集める。2006年に『買えない味』(筑摩書房)でBunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。2012年に『野蛮な読書』(集英社)で第28回講談社エッセイ賞受賞。『サンドウィッチは銀座で』(文藝春秋)などエッセイが常に人気。最新刊『忘れない味 「食べる」をめぐる27篇』(講談社)
会社勤めをしたことがない、と言うと、よく驚かれます。大学在学中から書く仕事を始め、そのまま30年以上、食や暮らしをテーマに文筆業を生業(なりわい)としています。
子どもの頃から無類の本好き
岡山の倉敷で育った私は、子どもの頃から無類の本好きでした。冬、3歳下の妹とこたつに入って、家事をしている母のそばで本を読む。それが、私にとっての家族の風景。本を読み、本に触れているだけで安心できる子でした。
学校では、休み時間になると図書室へ走り、棚の端から順番に借りて読みました。『いやいやえん』(中川李枝子/作、大村百合子/絵)や『アンネの日記』(アンネ・フランク著)、『点子ちゃんとアントン』(エーリヒ・ケストナー著)……。思い入れのある本はたくさんあります。自宅にあった百科事典を「あ」から順番に読むことも楽しかった。読み進めるうちに、自分が大きな宇宙のなかにいることを感じたものです。
本を読むと、「ここではないどこか」に、瞬時に行ける。本は、わくわくするような楽しさを確実に連れてきてくれる。だから、手を伸ばさずにはいられませんでした。読むことで、自分のなかに何か聖域のようなものが築かれる実感もありました。私にとって本は、「自由なもの」の象徴でした。
実は、高校を卒業するまでの私には、常に違和感がまとわりついていました。その息苦しさから自由になる手段が本だったのです。