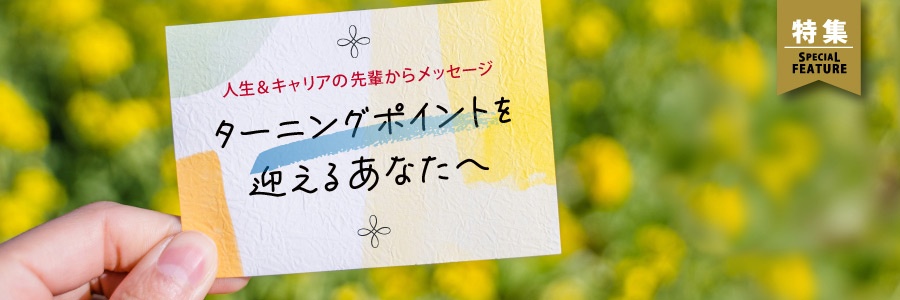人生には思いもよらぬことが起きるもの。肩の力を抜いて柔軟に「私の生き方」を見つけていこう――。先輩たちが半生を振り返って贈る、珠玉のメッセージ。日経WOMANの看板リレー連載を、ARIA読者にお届けします。小説家・井上荒野さんの第1回。作家・井上光晴氏を父に持ち、たくさんの本と家族の会話と共に育ちます。「人間は何者かにならなければならない」というのが父の教え。しかしユニークな校風の高校に進学してもやりたいことは見つからず、挫折感を味わうのでした。
(1)「何者かになる」ことを探すつらさ ←今回はココ
(2)準備ないままデビュー、自信を喪失
(3)私にとっての「スペシャル」が小説
小説家
 1961年東京都生まれ。成蹊大学文学部卒業。89年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞を受賞。執筆活動のかたわら、児童書の翻訳家としても活躍。04年『潤一』で島清恋愛文学賞、08年『切羽へ』で直木賞受賞。11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、16年『赤へ』で柴田錬三郎賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞。他に『もう切るわ』『森のなかのママ』『さようなら、猫』や、父について綴ったエッセイ『ひどい感じ 父・井上光晴』、両親と瀬戸内寂聴さんとの関係をモデルにした小説『あちらにいる鬼』など著書多数。
1961年東京都生まれ。成蹊大学文学部卒業。89年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞を受賞。執筆活動のかたわら、児童書の翻訳家としても活躍。04年『潤一』で島清恋愛文学賞、08年『切羽へ』で直木賞受賞。11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、16年『赤へ』で柴田錬三郎賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞。他に『もう切るわ』『森のなかのママ』『さようなら、猫』や、父について綴ったエッセイ『ひどい感じ 父・井上光晴』、両親と瀬戸内寂聴さんとの関係をモデルにした小説『あちらにいる鬼』など著書多数。
幼稚園では毎朝泣いていた。送ってきた母と別れるのがいやで。といっても、それは大人たちが言っていたことで、私にしてみればさしたる理由はなかった。ただ昨日も泣いたから、今日も泣いていたのだった。泣き止むきっかけが分からず、そのことを説明できなかった。それは私が私という人間になった、最初の記憶であるようにも思える。
この頃のことではもう一つ、印象深い出来事がある。あるとき園長先生が、園児たちの前で何か注意か訓話をした。お友達とは仲良くしなければいけません。なぜなら、お友達はとっても大切なものだからです。覚えていないのだが、たぶん、そういうふうなことだったろう。話し終えると、園長先生は、分かりましたか? と聞いた。はーい。園児たちは元気よく返事をして手を挙げた。
はーい、と私も言った。でも、手は挙げなかった。間が悪いことに、私はこのとき園長先生の真正面にいた。園長先生はつかつかと私に近づいてきて、「あなたは分からないの?」と言った。私はびっくりして首を振った(「ちゃんとわかってる」という意味で)。「はーい」と答えるのと同時に、手を挙げるのは習いだった。でも、園長先生は「分かった人は手を挙げて」とは言わなかったのだから、挙げなくてもいいのだろう。私はそう考えたのだ。これは理不尽についての最初の記憶。それから、言葉というものに対する自分の態度の、最初の表明であったのだろうと思う。