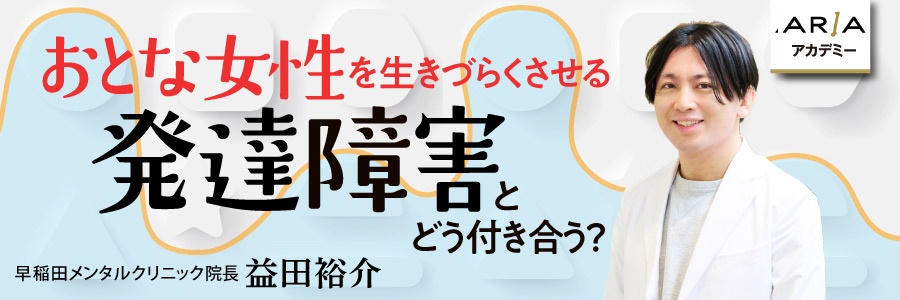遠く離れた実家で、父が孤独死していた――。この連載では、東京でフリーランスエディターをしている如月サラさんが、突然の父の死と母の遠距離介護に向き合う日々をつづり、大きな反響を呼んできました。今回はいよいよ最終回。予想だにしなかった形で訪れた父の死が如月さんにもたらしたものは、決して悲しみやつらさだけではありませんでした。
ある寒い日、遠く離れた実家で父がひとりで死んでいたのが見つかった。前年の夏、熱中症で倒れた母は認知症と診断され、専門病院に入院していた。父ひとりの実家になかなか帰る気になれず、コロナ禍を理由に私はそれから実家に一度も帰らなかった。父は半年後に自宅で倒れ、発見されたのはその1週間後だった。
母は入院先から高齢者施設に入居し、実家は無人のままそこにある。母をわずかな時間見舞うため、そして実家の整理のために月に1回、往復する日々が始まり、私は疲れ切っていた。そんな日々でも次第に気づいたことがある。
父の葬儀で25年ぶりに年上のいとこと再会
ある晴れた休日の昼、私は目黒川の見えるレストランで8歳年上の女性と向かい合っていた。彼女は私の父方のいとこで、こうやって会うのは25年ぶりだった。
母方の親戚とは、皆、住まいが近いこともあり折々に顔を合わせて育ってきたが、少し距離のある父方の親戚とはどうしても疎遠になってしまっていた。幼い頃に会ったきり、その後はごくたまに慶事や弔事で顔を合わせる程度だった。
そのいとこは、特に女性は地元にとどまりがちな保守的な故郷から、私よりうんと早くに東京に出て、華やかなエンターテインメント業界で責任を持って働いてきたワーキングウーマンだった。堅い仕事の多い親戚筋の見えぬ慣習を吹き飛ばし、東京で活躍する彼女に私はひそかにあこがれていた。
私もあこがれの出版社で雑誌のエディターになれるかもしれない。そう信じて25歳で思い切って東京に出ることを選んだのも、彼女がつけてくれた足跡をどこかでたどったところがあったのだろう。
とはいえ、普段からやり取りをしていたわけではない彼女とは、私が東京に出てきてすぐに一度だけ食事を共にした後、特に連絡を取り合うことはなかった。自分は自分の道筋をつけるのだと、若い私がひとりで踏ん張ろうと決めたからだと思う。
父の葬儀で久しぶりに再会し、半年余りたった頃にランチに誘ってくれた。皿に盛られた美しい料理をいただきながら、既に両親とも亡くなった彼女と、お互いの来し方行く末についてとりとめもなく話す。とっくにこの後の生き方を決めている年上の女性を、私は頼もしく誇らしく感じた。
対等に話せるようになるまで25年かかったのだなと思った。でも父が死んでいなければ、おそらくこうやって再び会うこともなかったのだ。