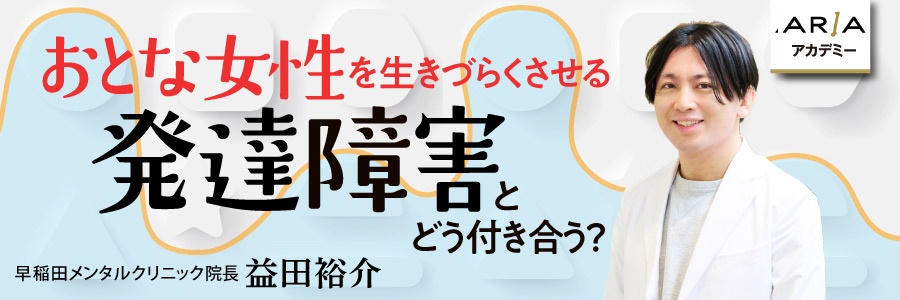遠く離れた実家で、父が孤独死していた――。東京でフリーランスエディターをしている如月サラさんはある日、予想もしなかった知らせを受けます。如月さんは50代独身、ひとりっ子。葬儀、実家の片付け、相続に母の遠距離介護など、ショックに立ち尽くす間もなく突如直面することになった現実をひとりで切り抜けていく日々をリアルにつづります。
叔父の話で初めて知った、若き日の父のこと
冬。遠く離れた故郷で父がひとりで死んでいたのが見つかって、警察による検視と葬儀と火葬まであっという間の2日間が過ぎた。(前回記事参照「ある寒い冬の日、遠く離れて暮らす父が孤独死していた」)
コロナ禍なのでごく少人数ではあったけれど、母方の叔父や叔母、これまでほとんど会ったことのない父方の叔父やいとこたちが来てくれた。
父の弟に当たる叔父は、私の知らない若い頃の父の話をしてくれた。高校時代に合唱部の部長だったこと。やけにモテていたこと。更年期障害で動けない祖母の代わりに兄弟の食事を作ってくれていたこと。まだ父の死を現実のものと受け止め切れていない私に、笑顔混じりのとりとめのない思い出話は、大きななぐさめになった。
今、ただの物体となった父親の肉体は焼かれて、確かに世界の一角を占めていたその存在は消え去ろうとしている。そんな時に残っていくのは、こんなたわいのない記憶だけなのだろうと思った。
すべての儀式が終わると、私はひとり取り残された。話す相手もいなかった。一緒に泣ける人もいなかった。これからの相談ができる家族もいなかった。葬儀場から骨つぼを抱えて歩いて実家へ帰った。
日が暮れてゆく。父がいつも座っていた台所のテーブルの一角に座って、テレビを見ながら近所のチェーン店で買ってきたお弁当を食べた。
ランチの誘いには乗りたいけれど、その後が怖い
地元の友人に、時間と気力があれば日曜日にランチでもしようと連絡をもらった。ひとりでいるのは心細すぎたから行きたかったけれど、ランチの後にまたひとりで誰もいない実家に帰るのが怖かった。
「よければ実家に来て1日一緒にいてくれる?」
無理を承知で頼んでみると、快く受け入れてくれた。話すうち、せっかくなら少しでも家を片付けよう、手伝うよという話になった。