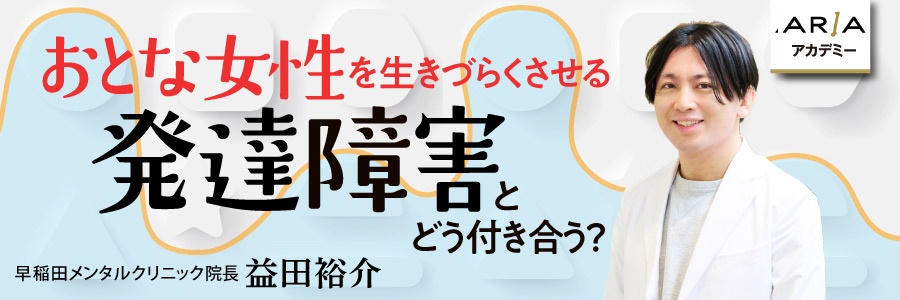遠く離れた実家で、父が孤独死していた――。東京でフリーランスエディターをしている如月サラさんはある日、予想もしなかった知らせを受けます。如月さんは50代独身、ひとりっ子。葬儀、実家の片付け、相続に母の遠距離介護など、ショックに立ち尽くす間もなく突如直面することになった現実をひとりで切り抜けていく日々をリアルにつづります。
「お父さんがベッドの脇の床に倒れている」
今年の1月半ばに、独り暮らしだった父(84)が遠く離れた実家の自室で倒れて亡くなっているのが見つかった。死後1週間たっていた。
父が独り暮らしになったのは、昨年の夏に母(82)が熱中症で倒れたことをきっかけに長期入院してからだ。母のことばかりに気を取られて、父はなんとかやっているものだと思っていた。思うようにしていた。
父と私の意思疎通は、月に1回の、母の入院費の支払額を連絡するときだけだった。病院からの請求書は私が東京で受け取り、支払いは父にお願いしていたのだ。
母の入院に納得していなかった父と言い合いになるので、私は電話を次第にかけなくなった。誕生日にも。お正月にも。
そして1月の半ば。今月の入院費を連絡しようと何度か電話をかけたが、出ない。嫌な予感がした。
実家の鍵を預けてある叔母に電話をして、様子を見に行ってくれないかと頼んだ。東京の自宅で仕事をしながら不安が募っていった。16時頃、叔母から電話がかかってきた。
「お父さんがベッドの脇の床に倒れている」
「倒れて苦しんでいるんですか、もう死んでいるんですか」
叔母は「うーん……」と言った。
生きていれば119番。死んでいれば110番。その知識はあった。
「ああ……死んでいるんですね、110番してください」
そう言うのが精いっぱいだった。
翌日飛行機で故郷へ、まず向かったのは警察
羽田から故郷への最終便は19時頃。今から準備すれば間に合うかもしれない。しかし私の東京の家には2匹の猫がいる。この帰省は1週間近くかかるだろう。その間、猫をどうしよう。
そんなことを考えながらグルグルグルグルと狭い部屋の中を歩き回った。何から手を着ければいいか分からなかった。
そのうち、警察から「これからしばらくののち、事情聴取のお電話をします。明日の朝にご遺体の解剖をしますので、明日来てくだされば大丈夫です」と電話がかかってきた。明日の朝一番の羽田からの便を予約し、とにかくまずは猫を預けておこうとペットホテルに連れていった。
若い警官は、ご遺体、と言った。
父は、遺体になってしまったのだ。