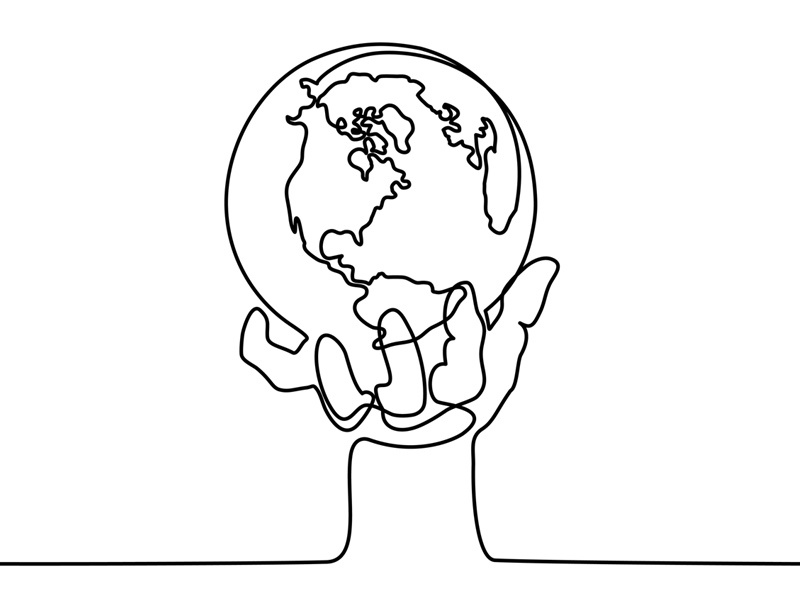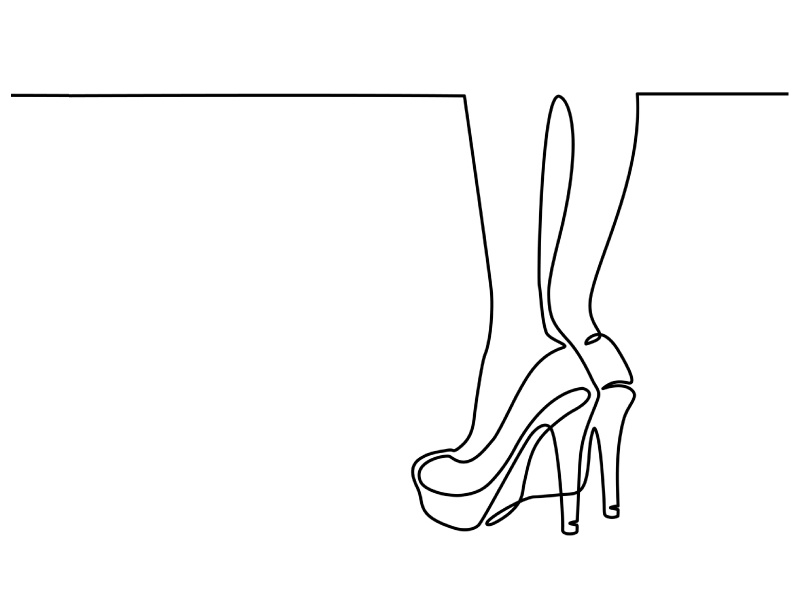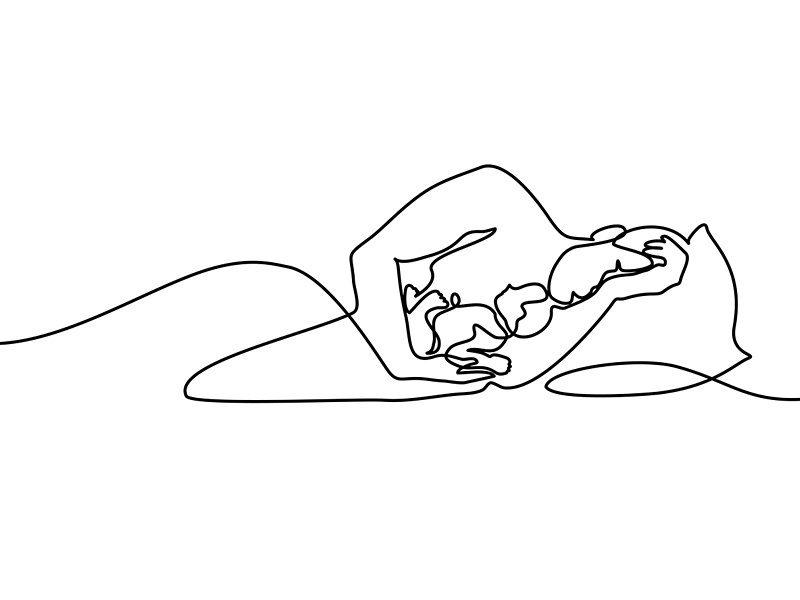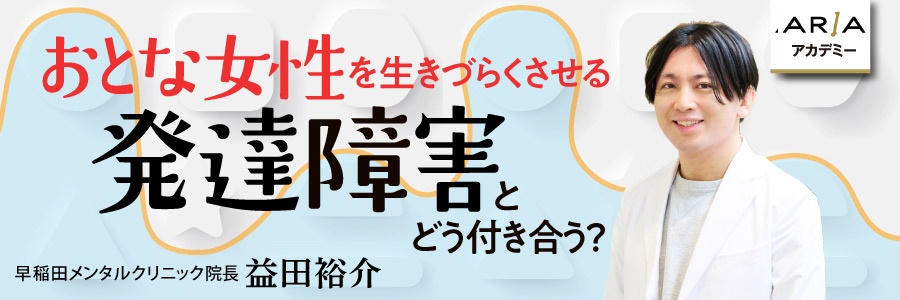「唐突だね」
「そうでもない。私が歌を好きなのって高校生のときにホームステイ先で『天使にラブ・ソングを…』を観たからよ」
「知ってるよ。だからあの映画も観たんだよね」
当時は今みたいにミュージカル映画が量産されておらず、歌を題材にした映画は貴重だった。だからどんなマイナーな映画でも観に行っていた。でも、若いころは恥ずかしかったり心の内を観られるのがいやだったりで、自分で歌う勇気はなく、観客に徹していたのだった。
「聴いたり見たりするのももちろん好きだけど、やっぱり自分でも歌えたら幸せだと思うの。もうこの歳になると、恥ずかしいとかそういう感情もないですし」
「あなたも立派なおばさんになりましたね。いいと思うよ。早くガブリエラの歌を歌えるようになって」
「あれはゴスペルかグリーか、どっち?」
「スウェーデン民謡じゃない?」
「都内に教室あるかなあ……」
やがて隣から小さな鼾(いびき)が聞こえてくる。私は枕元の抽斗から耳栓を取り出し、両耳に入れる。幸せな生活は与えてもらうものではなく、自身の努力と創意工夫の上に成り立つ。これからの人生で私はどんな歌を歌ってゆくのか。心躍るような歓びの歌も、耳を覆いたくなるような悲しみの歌も、できることならずっと夫に聴いていてもらいたいと願いながら、私も眠りに落ちた。
文/宮木あや子