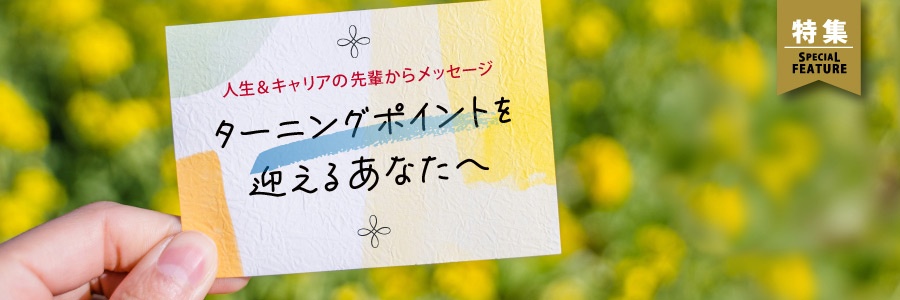考えすぎず、訪れたチャンスに身を任せてみることも大事
──次々と責任ある地位に就くことに躊躇などはないのでしょうか?
竹田 産休明けに日本の法務部のリードだとか、そんなにすぐに執行役員になっていいのかとか、やはり躊躇はします。ですが、せっかくのチャンスですし、あまり先のことを考えても仕方ないなと。性格なのでしょうか。ベストを尽くしてもダメだったら仕方がない、自分にできることをできる範囲でしっかりとやろう。何かきっかけがあってそうなったわけではなく、できるだけのことをしてもダメだったらポジションを変えてもらおうと、一歩引いて考えてきたんだと思います。
──役員にならなければ見えなかったこと、なったからこそ気づいたことはありますか?
竹田 やはり視野は広がりました。例えば経営会議での情報収集や意思決定の仕方はとても勉強になり、会社の方向性、日本だけでなくグローバルな視点においても、すごく意識するようになりました。社内でもネットワークが増え、引き出しが増えたと思いますし、それが、自分の仕事にも結びついてきています。改めて自分を振り返ると、弁護士になったのに、今では法律以外のことも結構やっているなと。チームを作るとか、予算管理とか、経営陣とのやりとりとか、自分としての選択肢はかなり増えました。でも、私は経営者になりたいという気持ちは全くなくて、あくまでベースは法律家です。
──竹田さんのような女性役員を日本企業に増やすためにできることとは何でしょうか。
竹田 例えばフィリピンのアクセンチュアでは、男性と女性のマネジング・ディレクターの数は半々です。なぜそれが達成できているのかを聞いて感じるのは、土壌があるということ。女性が活躍するためのインフラがあるのです。やっぱりインフラは必要だと思います。外で活躍し、家に帰ってもまた仕事(家事)があるという状況では疲弊してしまう。女性が、長期的に元気に仕事ができる環境を整えていかなきゃいけないなと思います。例えば、私も料理の作り置きサービスを利用していますが、そういったものを気兼ねなく使えるような状況になればいいと思います。周りの人に話すと、料理については「そこまで頼むの?」という反応があります。それが少しずつなくなっていけばいいなと。インフラが整い、無駄なバイアスがとれ、そういうものをもう少し自由に使えるようになると、女性は活躍しやすくなるのかなと思います。長期的には、ジュニア層から若手の世代がそういう考えになってくれば、だんだん変わっていくと思いますし、短期的には、職場のフレキシビリティ、在宅勤務とか、働く時間を自由に調整できるなど、それだけでもだいぶ変わると思いますね。私自身、子どもを持ちながらフルタイムでここまでやってこられているのは、職場のフレキシビリティがあってこそで、会社には感謝しています。

──働く女性自身にできること、すべきことはありますか。
竹田 あとは、キャリアの断絶に対するマイナス意識がなくなればいいなと思います。例えば夫の転勤を理由に仕事を辞めて海外に行き、一度専業主婦になると、戻って来てもなかなか再就職への踏ん切りがつかないという話を聞いたことがあります。それはすごくもったいないと思います。私の同級生の弁護士でも、そういう人は珍しくありません。確かに4、5年ブランクがあると最初は大変かもしれないですが、やり始めればできるというケースもきっと多いはず。動いてみないと分かりません。また、たとえ制約があってもできることはあると思います。女性側も受け入れ側もそういう寛容さを持って欲しいなと思いますね。
──最後に、働く女性へ向け、竹田さんからエールをお願いします。
竹田 責任あるポジションに就いてみないかとか、自分がやったことのない分野にチャレンジしてみないかと言われた時は、いろんな選択肢を思い巡らせる前に、まずは直感を頼りにすること。そういうチャンスが自分にくるのは、周囲からの期待もあるからなので、責任が重そうで嫌だなと思っても、とりあえず新たな環境に身を投げ入れてみるといいと思います。あまり先を考えすぎないというか、チャンスをきちんとつかんでいくことが大事だと思いますね。そういうことの積み重ねで、自分でも気づいていなかった自身の特長に気づくこともありますし、また、視野や選択肢が広がり、キャリアはその上に成り立っていくものだと思います。状況は変わりますから、すぐに白黒付けすぎないことです。これからは細くても長く働くことが大事だと思います。テクノロジーも進化しているので、働き方はいろいろあります。辞めるというのは白黒付けてしまうことなので、グレーでもいいから細く長く続けてほしい。ペースを上げたり下げたりしながらでも、続けていくと見えてくるものはありますし、道は拓けて行くと信じています。私自身も、そういう選択を続けてきたからこそ今があると思っています。
取材・文/鈴木友紀 写真/小林大介