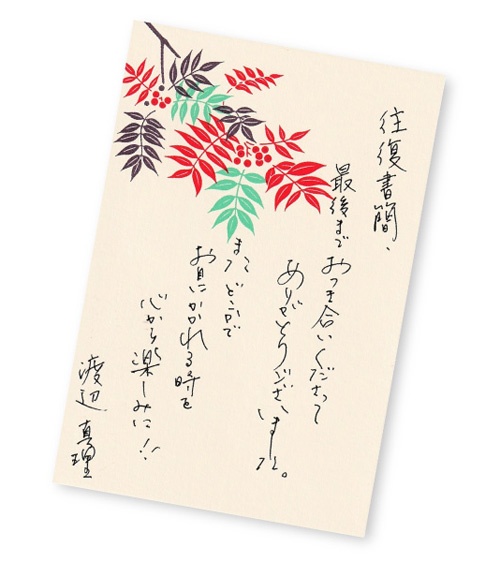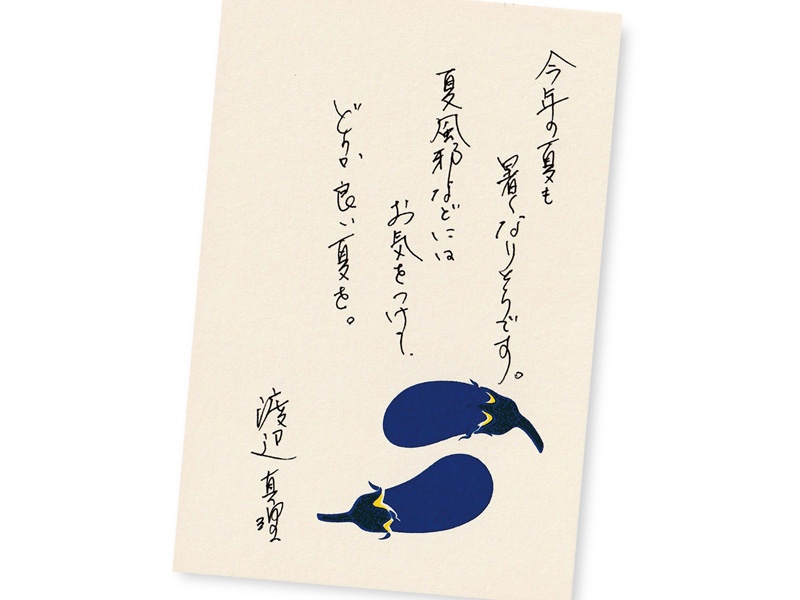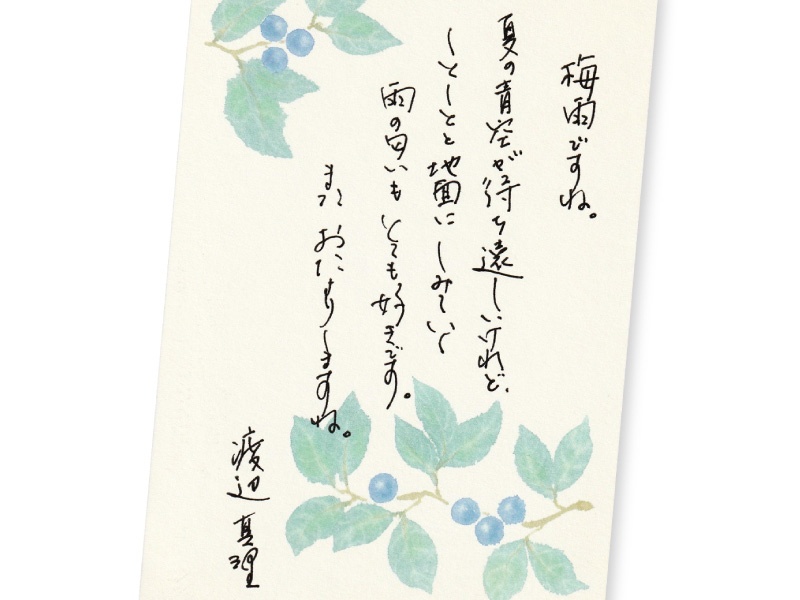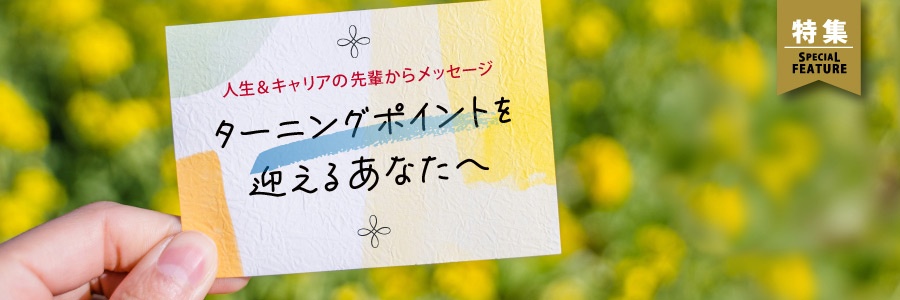折りに触れ自分の中の祖母に語りかけている
母と暮らしながら、母との別れをいつも考えているわけではもちろんないのですけれど、頭のどこか隅っこにぼんやりとした影のように別れの予感は居座っています。
不思議なものですね。先ほど、時間だけが別れを癒やしてくれる友達かもしれないと書きましたけれど、その時間が、どんな生き物にも同じ速さで流れながらいつか母を連れ去っていくわけですから。時間は優しくも残酷で、怖いけれど救いでもあるように感じます。
母の母、私にとって大好きだった祖母を亡くしたときの心持ちをよく覚えています。106歳で他界した祖母はだんだんと眠っている時間が増え、だんだんと食事の量が減り、ペロリと一度でたいらげていたプリンも、最晩年にはひと口だけで満足するようになりました。ありがたいことに痛みなどはなかったのでつらそうではなく、植物が少しずつ枯れていくような姿、眠りに近づいていく横顔を孫の私にも見せてくれているようでした。
今でも、祖母が住んでいた辺りを通るのは祖母の不在をわざわざ確認するようで、気は進みません。そういう意味では恐らく、祖母の不在はいつまでたっても私にとって痛手であり続けるのだと変に確信してもいます。けれど、老いていく姿、枯れていく様子を間近で見守っているとき、私自身の中に祖母という存在が少しずつ入ってくるような不思議な感覚を覚えたものでした。生前のように実際の会話はできなくても、折りに触れ自分の中の祖母に問いかけ、祖母だったらどうするだろう? と考える癖は、祖母が逝って数年、随分と私の中で定着してきました。
母を送る日――考えないわけではないけれど、そのときの私なりに受け止めてみます。きっと母も、娘のことを案じながらも、どこかで大丈夫だろうと高をくくって、疲れた体から解き放たれるのではないかな、そんなふうにも感じます。母の不在に、しばらくは急に涙があふれたりするかもしれないけれど、そのうち私は私の中の祖母や両親と対話しながら生きていくことが分かっているので。
思いついたままに、つらつらとやり取りさせていただいた往復書簡でしたが、最後まで、ありがとうございました。皆さまにとって、今日という一日がすてきな日でありますよう。感謝をこめて。
※1 『暮しの手帖』2019年8~9月号157ページ(暮しの手帖社)
文/渡辺真理